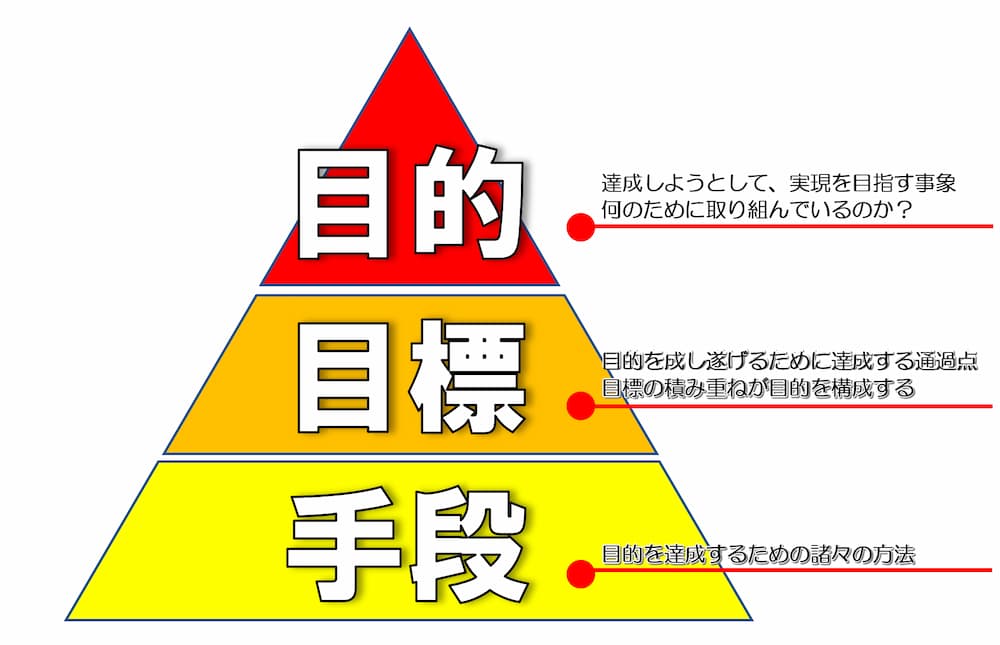バスケットボールに関わる全ての皆様にどうしても考えていただきたいことがありこの投稿をしています
坂の上の夢
関西女子学生バスケットボール連盟1部リーグ所属MWU LAVYS Basketball Teamのヘッドコーチが
大学日本一という夢の実現に向けて日々登り続ける坂道の記録
バスケットボールのコーチングを心・技術・戦術・体力の側面から深く追求していきます
『Podcastで聴くコーチングのヒント 坂の上の夢の声』というタイトルのポッドキャスト で声の配信も行っています!
2025/06/05
バスケットボールを安全にプレイできる環境を求めて
2025/03/13
「問題」の捉え方が2つあるから確認しなきゃいかんな
人生訓②
2025/03/10
2つのspeed kills idea
その中でcoach Lisaroが「speed kills idea」という言葉を使っている
速さは技術だ!
このYoutuberでcoach Lisaroが語っているspeed kills ideaは
防御側の連携のスピードは攻撃側の思考に勝るというスピードの正の側面とその可能性についての話
その瞬間に3on4を攻め切られたら
あとはシュートが落ちることを期待するしかない
そこを防御側の「思考速度」「移動速度」を上げて瞬間的にチャンスが生まれたとしてもそれを瞬殺する防御力を目指そう!
という考え方はシュートが落ちることを期待するよりも魅力がある
「移動速度そのものを上げること」
「ルールを簡単にすること」
「判断基準を明確にすること」
「コミュニケーションを徹底して他者に伝えること」
2025/03/07
自分の外側に正解を求め続ける旅に終わりは来ない
「外側の正解を求め続ける世界」
という記事がある
コーチングをしていく上でもとても大事な考え方だと思う
コーチングする自分自身にとっても
プレイヤーにとっても
inputしてもinputしても
「もっと他にinputすべきことがあるんじゃないか」
「自分が知っていることの他にもっとよい正解があるんじゃないか」
っていう強迫観念にかられることがある
「無知の知」というソクラテスの言葉があるが
自分には知らないことがあるという自覚は人生を生きていく上でとても大事なこと
「自分はもう多くのことを知っている」
「自分はもういろんなことができるようになっている」
と思った瞬間にそこで成長が止まってしまうって現象は
経験を積めば積むほど
知識量が増えれば増えるほど
起こる可能性が高くなる
しかし
時にこの自分の外側に正解を求める志向は自己肯定感を下げてしまうことがある
競技スポーツに臨むアスリートにとって
この志向は勝負の瞬間に「自分の中にあるもの」ではなく
「自分の外にあるもの」に頼ってしまう危うさを孕んでいる
競技の場に立ったアスリートは
勝負の瞬間に他者の手助けを受けることができない
だからどんな結果になろうとも
自分自身の中にあるもので勝負と向き合うしかない
それが競技スポーツの厳しさ
今その瞬間において自分自身の中にあるものを信じ切ることができなければ
無意識のうちに
「逃げる」
「他者のアイデアで動く」ことで責任を回避する
のいずれかの方策で「可能性の中に生き続ける」選択をし
自尊心を保とうとする
inputをすることで知的理解を高め
反復することで遂行力を高め
勝負の瞬間は覚悟を決めてoutputする
どんな結果が出ようとも結果は自分が引き受ける
そして次の成長に向けてまたinputしていく
コーチングする自分自身も
プレイヤーも
そんなそんな志向がもてるように自分自身と向き合っていきたいと思う
そして
人生を生きていく上でも
2025/03/05
階段登ったら後ろが崩れてた……コーチングのあるある
「成長」のメタファーでもある
ルパン三世や未来少年コナンに崩れる橋を渡ってるシーンがあったが
まさにあれっ^^;
知的な理解と体が了解することの違いか…
それでも同じ水準でぐるぐる回ってても成長はないので
元に戻った時には質的に改善しているスパイラルアップのイメージが一番いい
パフォーマンス構造を元に原因と課題を設定し
どの部分が欠けても良いコーチングににはならないが
正課外教育のクラブ活動で育つのは生徒?学生?それとも教員?
教員コーチのつぶやき
2025/01/20
●●が「●●以上のもの」であるか?
2024/12/03
「創り上げるコーチング」と「即興させるコーチング」
1年は長いようで短いようで…
毎年研究室のドアに貼り付けてある年間カレンダーに日々✕印をつけ
「未来」を見据えながら「今」の「位置」と目標への「距離感」確認しながら過ごしている
学生の成長には時間がかかる
当然ながら今日やったことが明日の試合で使えるわけではない
できたという「発生」段階の「粗形態」から
場面に応じた「分化」や「定着」がみられる「精形態」を経て
技術の遂行そのものは前意識的に処理し意識は外部へ向く「自動化」がみられる「最高精形態」に到達するまで
個人戦術もチーム戦術も育成には極めて長い時間がかかる
プレイヤーの身体が覚えるというのは知的に理解するのとは異なる長い時間がかかる
既に要素となる個人技術や個人戦術やグループ戦術を「最高精形態」の水準で獲得しているトップアスリートが集まったチームに「チーム戦術の決定」と「短時間での合わせ」を経て「試合で実践」するような「即興させるコーチング」と
個人技術や個人戦術から育成強化していかなければならない段階の「創り上げるコーチング」では明らかに距離感が異なる
当然目標に至るプロセスも異なる
代表チームのレベルであっても
「創り上げる」タイプのコーチングもあれば
「即興させる」タイプのコーチングもある
どちらがフィットするかはプレイヤーの到達している水準の高さ
ということになるのだろう
全日本男子のコーチングに関して様々な意見が出されているが
ホーバスは「創り上げる」タイプのコーチングに強みがあるのだと思う
こういった現状のプレイヤーの質とコーチングのスタイルについて
きちんと議論をした方がいいんじゃないかなぁ
チームは明日から2024シーズンの最後の舞台が開演
勝負だ
2021/07/16
目に見える問題に対応することと目に見えない問題に対応すること
問題解決型思考では
目標を明確に設定し
現状を正確に評価したら
問題は眼前に立ち現れてくる
と表現する
なので問題は「目標値と現在値との差」と定義することができる
ということは
問題には
①「あるべき状態を達成しようと取り組んだが悪い結果になってしまった問題」
②「あるべき状態を達成することに取り組んでいない問題」
の2種類があるということになる
①は「やったんだけど失敗したこと」が問題
②は「やらなかったこと」「やれなかったこと」が問題…
①と②はいずれも、あるべき状態と今の状態に差があるという点は同じ
でも
①はいわゆる具体的な失敗だから目につくので認識しやすい
しかし
②は具体的な失敗として目の前に現れてこないから「脳内であるべき姿を映像として流しながら目の前の現象を観察する」というか「目標の像と実際の像の2画面を重ねて違いを見抜く観察」ができない限り絶対に認識できない
そのため
問題解決は一般的に①への対応に偏ってしまうことが多い
目の前に具体的な①の問題が現れることは、スポーツ指導の場に限らず、仕事や日常生活の場の中でも頻繁に発生する
だから
①の問題に対応するときは、「今目の前に現れていない②の問題があるかもしれない」「今目の前に現れていない②の問題を解決したら、今目の前に現れている①の問題はそもそも起こらないかもしれない」などの可能性を検討した上で、「今目の前に現れてる①の問題に対応すること」の意義や重要性や必要性が認められる場合に①の問題に対応し始めるといった思考の習慣をつけたい
そうしないと
次から次へに現れる問題の渦に巻き込まれ、「問題だ問題だ……」ってなってしまう
問題解決力が高いという自己効力感があるほど、無意識に悪循環にはまり込んでしまう危うさがあることを理解しておく必要があるなと思う
2021/06/25
無意識の力って凄い
バスケットボールを安全にプレイできる環境を求めて
バスケットボールに関わる全ての皆様にどうしても考えていただきたいことがありこの投稿をしています 女子の大学カテゴリーですが1990年代からずっと現場で指導する教員コーチとしてどうしても考えていただきたいことです それは「強度(intensity)」についてです 歴史的にバスケ...
-
試合期にはいつも見直すメモ 試合後の反省もあって少しずつバージョンアップしてきたもの このあいだ応援に駆けつけてくれた卒業生と試合前に見ていたこのメモの話になり 「それください!」って言われたのでアップしてみました コーチによって試合への臨み方はひとそれぞれ...
-
今日は13:00からBSプレミアムにて「坂の上の雲」を一挙放送している. 午後はずっと観ている. かつて,小説「坂の上の雲」を読んで,司馬遼太郎が描く様々な「指揮官」の姿に,指揮官としてのコーチいかにあるべきかを考えさせられた.だから,ブログタイトルを「坂の上の夢」にした(笑...
-
長い長い時間をかけて練習をしてきても 本当の勝負はほんの一瞬 「鍛錬千日之行 勝負一瞬之行」 かつて甲子園を湧かせた 池田高校野球部監督蔦文也氏の言葉 練習でどんなにシュートを打ち込んでも 本当の勝負の一本を決める力がなければ 勝者にはなれない 努力をする...